倉庫管理は、事業の効率性や顧客満足度を大きく左右する重要な要素です。
商品のスムーズな入出庫、正確な在庫管理、そして作業効率の向上は、コスト削減や生産性向上に直結します。
今回は、倉庫業務の基本となる「ストックエリアとピッキングエリアの使い分け」、「ロケーション管理の種類」、そして「ロケーション番号の設計方法」について、分かりやすく解説していきます。
ストックエリアとピッキングエリアの賢い使い分け
倉庫内のスペースは大きく「ストックエリア(保管エリア)」と「ピッキングエリア(出荷準備エリア)」に分けられます。
この2つの役割を理解し、適切に使い分けることが、倉庫運営をスムーズにする鍵となります。
ストックエリア:大量保管で効率を追求する「倉庫の奥」
ストックエリアは、その名の通り大量の商品を効率的に保管することを主な目的としたスペースです。
まだ出荷予定のない商品や、まとめて入庫された商品を一時的に保管しておく「倉庫の奥」のような場所をイメージしてください。
ストックエリアの特徴
- 保管効率を最重視: 棚の高さを最大限に活用したり、奥行きの深い棚を使用したりして、できるだけ多くの商品を保管できるように設計されます。
- 機械活用が中心: 大量の商品を移動させるため、フォークリフトや自動倉庫システムなどが積極的に活用されます。
- 保管のしやすさ優先: ピッキングの動線よりも、保管されている商品の安全確保や管理のしやすさが優先されます。
- ケース・パレット単位での保管: 個々の商品ではなく、箱やパレットといったまとまった単位で保管されることがほとんどです。
どんな時に活躍する?
- メーカーから一度に大量の商品が届いた時
- まだ出荷予定日が先の商品の長期保管
- 災害時や繁忙期に備えて、多めに在庫を確保しておく場合
- 個々の商品ではなく、箱単位やパレット単位で在庫を管理したい時
ピッキングエリア:迅速な出荷準備を可能にする「倉庫の手前」
一方、ピッキングエリアは注文に応じて商品を効率的に取り出し、出荷準備を行うことを主な目的としたスペースです。
お客様の注文に合わせて、必要な商品をすぐに取り出せる「倉庫の手前」のような場所です。
ピッキングエリアの特徴
- ピッキング効率を最重視: 作業員が歩く距離を最小限に抑えたり、取り出しやすい高さに商品を配置したりと、いかに早く正確に商品を取り出せるかが重要視されます。
- 取り出しやすい工夫: スライド式の棚、傾斜のついた棚(シュート)、小分けの棚など、手作業での取り出しやすさを追求した設備が導入されます。
- 最適な動線設計: 作業員の移動経路が短くなるように、人気商品や出荷頻度の高い商品をより手前に配置するなど、動線設計が非常に重要になります。
- バラ・小ロット単位での保管: 注文に応じて個々の商品(バラ)や、小ロットの単位で保管・取り出しが行われます。
どんな時に活躍する?
- お客様から注文が入った時、商品をピックアップする際
- 複数の商品をまとめて出荷するために、各商品を少量ずつ取り出す時
- ギフトラッピングやセット組みなどの加工を行う前段階
- オンラインショップなど、少量多品種の出荷に対応する時
ストックエリアとピッキングエリアの関係性
これら2つのエリアは、異なる役割を持ちながらも密接に連携しています。
ピッキングエリアの在庫が少なくなると、ストックエリアから商品を補充します。この作業を「品出し(補充)」と呼びます。
この品出し作業がスムーズに行われることで、ピッキングエリアで常に商品が欠品することなく、円滑な出荷作業が維持できます。
例えるなら、大型スーパーの「バックヤードにある倉庫(ストックエリア)」と「陳列棚(ピッキングエリア)」のような関係です。
それぞれの役割を分担することで、倉庫全体の作業効率が向上し、より迅速かつ正確な出荷が可能になります。
倉庫の「住所」を決める!ロケーションの種類と選び方
倉庫内の商品の保管場所を管理する方法をロケーション管理と呼びます。
このロケーション管理には、主に「固定ロケーション」と「フリーロケーション」の2つの方式があります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、貴社の運用に合った方式を選ぶことが大切です。
固定ロケーション:慣れと安定性重視
固定ロケーションは、特定の商品を常に決まった場所(ロケーション)に保管する方式です。
メリット
- 作業の効率化: 商品の保管場所が固定されているため、作業員は場所を覚えやすく、ピッキングや格納作業の習熟が早まります。
- 在庫管理が容易: どこに何があるか一目で分かり、目視での在庫確認や棚卸しが比較的簡単です。
- 新規作業員の教育が簡単: ロケーションが決まっているため、新しい作業員でも早く作業に慣れることができます。
デメリット
- スペースの非効率な利用: 商品の入庫量にばらつきがあると空きスペースが発生しやすく、倉庫全体の保管効率が低下する可能性があります。
- 柔軟性の欠如: 商品の入れ替わりや保管量の変動に対応しにくく、レイアウト変更に手間がかかります。
- 特定のロケーションへの偏り: 人気商品などのロケーションに偏りが出やすく、作業員の移動動線が長くなる場合があります。
フリーロケーション:スペース最大限活用型
フリーロケーションは、空いているロケーションに自由に商品を格納する方式です。
メリット
- スペースの効率的な利用: 空いている場所に自由に商品を格納できるため、倉庫スペースを最大限に活用できます。
- 高い柔軟性: 商品の入出庫量や種類が頻繁に変わる場合でも、柔軟に対応できます。
- 保管能力の最大化: 理論上、倉庫の最大収容能力に近い状態で運用が可能です。
デメリット
- システム導入が必須: どの商品がどこにあるかを正確に管理するためには、WMS(倉庫管理システム)などの導入が不可欠です。
- 作業の複雑化: システムがない場合、商品を探すのに時間がかかり、ピッキングミスなども発生しやすくなります。
- 新規作業員の習熟に時間: システム操作の習熟が必要なため、新しい作業員が慣れるまでに時間がかかる場合があります。
最適なロケーション方式の選び方
どちらの方式が最適かは、取り扱う商品の種類、入出庫頻度、倉庫の規模、そしてWMSなどのシステム導入の可否によって異なります。
自社の状況を考慮し、最適な方式を選択しましょう。
迷わない!分かりやすいロケーション番号の振り方
効率的な在庫管理と作業の迅速化には、誰にとっても分かりやすいロケーション番号の設計が不可欠です。ロケーション番号は、倉庫内の商品の「住所」のようなもの。以下の4つの要素を階層的に組み合わせることで、直感的で管理しやすい番号体系を構築できます。
ロケーション番号の構成要素
① 場所(大区分):倉庫・工場・配送センターの識別
複数の倉庫や工場、配送センターを運用している場合に、それぞれの施設を識別するコードをロケーション番号の先頭に付与します。
- 例: TKY(東京倉庫)、OSK(大阪工場)、NGY(名古屋配送センター)
② 階層(中区分1):建物の階数
建物が複数階層になっている場合は、階数を表す数字やコードを続けます。
- 例: 01(1階)、02(2階)、B1(地下1階)
③ エリア(中区分2):機能別・商品別の区画
各階層をさらに細かく区切ったエリアを識別するコードを付与します。商品の種類(常温品、冷蔵品、危険物など)や、入出庫の頻度に基づいて設定すると効率的です。
- 例: A(入荷エリア)、B(出荷エリア)、C(常温保管エリア)、F(冷蔵保管エリア)、Z(危険物保管エリア)
④ 棚の位置(小区分):列・連・段
具体的な棚の位置を示す詳細な番号です。
- 列: 通路側から見た棚の並びを識別する番号。
- 連: 列の中にある個々の棚のブロックを識別する番号。
- 段: 棚の高さ方向の段を識別する番号(通常、下から数えます)。
- 例: 01(1列目)、05(5連目)、03(3段目)
ロケーション番号の組み合わせ例
上記の要素を組み合わせると、以下のようなロケーション番号が作成できます。
TKY-01-C-01-05-03
これは、
- TKY: 東京倉庫の
- 01: 1階の
- C: 常温保管エリアの
- 01: 1列目の
- 05: 5連目の
- 03: 3段目に商品が保管されていることを意味します。
このように、階層的に番号を振ることで、ロケーションの特定が容易になり、作業効率の向上、ミスの削減、そして新規作業員の教育コスト削減に繋がります。
貴社の倉庫の特性に合わせて、これらの要素を柔軟に組み合わせてみてください。
まとめ:効率的な倉庫管理でビジネスを加速させよう
今回の記事では、倉庫管理における「ストックエリアとピッキングエリアの使い分け」、「固定ロケーションとフリーロケーションの選択」、そして「分かりやすいロケーション番号の設計」という3つの基本要素について解説しました。
これらの知識を活かし、貴社の倉庫業務をさらに効率化することで、コスト削減や生産性向上、ひいては顧客満足度の向上にも繋がります。
ぜひ、本記事の内容を参考に、倉庫管理の最適化に取り組んでみてください。
倉庫管理に関するご質問やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
コーポレートサイトhttps://www.rin-tech.netを開設しました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。



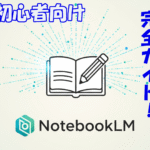
コメント