こんにちは!DXコンサルタントの林です。
今回も、全国シェア80%を誇る老舗製造業におけるDX推進の進捗をお届けします。
製造現場の改善、総務業務のデジタル化、そして営業戦略まで、多岐にわたる課題解決に向けた取り組みをご紹介します。
製造現場の変革:効率化への道 ⚙️✨
レイアウト改善:ホームセンターからの着想と社長の洞察 💡
製造現場の効率化は、まず作業スペースのレイアウト見直しから始まりました。
前回のアドバイスを受け、製造課課長がホームセンターの資材置き場を参考にし、長尺の弁棒を機能的に収納する「ポストパレット」案を提案。
一同からの良い反応を得ましたが、社長から「同時に使う部材は近くに置くべきという原則から外れていないか?」という鋭い指摘がありました。
この指摘を受け、課長はさらなる効率を追求したレイアウトの再考に着手。
現場の課題に対する深い洞察と、外部からの客観的なフィードバックが、真の改善に繋がることを再認識する事例となりました。
Kintoneピッキングアプリ開発:技術的課題とコンサルの支援 🧑💻
現場の効率を飛躍的に高めるために、Kintoneを活用したピッキングアプリの開発を進めています。
このアプリは、その日の全オーダーに必要な部品数を自動で合計し、一括でピッキングする「トータルピッキング」の実現を目指しています。
しかし、開発会社との打ち合わせで、「Kintoneの標準機能だけでは合計集計が難しい」「JavaScriptの専門知識が必要」という課題が浮上。
これに対し、私がREST APIの活用とJavaScriptの具体的なコーディング方法をレクチャーし、サンプルコードを提供することで技術支援を行うことになりました。
期限は来年3月。Kintoneで全ての業務を完結させるべく、開発チームと協力し、技術的な壁を乗り越えていきます。
総務業務のデジタル化:Excelからの脱却と効率向上 🧹✨
複雑な運賃計算のKintone攻略 🚚🗺️
総務部門では、見積もりや問い合わせで頻繁に発生する複雑な送料計算のデジタル化が喫緊の課題でした。
長年取引のある西濃運輸さんの運賃テーブルは、割引率や割増率が異なる3種類が存在し、ベテランの経験と知識に頼らざるを得ない状況でした。
これをKintoneでシステム化するため、以下の手順で仕組みを構築します。
- 基準となる「19年度100%運賃テーブル」をKmとKgをキーにKintoneで作成。
- 「全国市町村テーブル」を作成し、各市町村および町域ごとの増減率を設定。
これにより、届け先の「県→市町村」を選択し「重量」を入力するだけで、Kintoneが自動で運賃を算出。
属人化していた複雑な計算業務を、誰でも正確かつ迅速に行えるようになります。
職人技の重量計算をチェックボックスで簡易化 📏⚖️
運賃計算と並び、長年の経験が問われるのが製品の重量計算です。
特に地上式の場合、管の有無や地下寸法の変更によって細かく重量が変動するという、まさに職人技のような計算が必要でした。
この暗黙知をデジタル化するため、Kintoneの別画面で開発。
仕様書を見ながら該当項目をチェックボックスで選択していくだけで、Kintoneが瞬時に最終重量を計算する仕組みを構築します。
これにより、ベテラン事務員への確認作業が不要となり、業務の効率化と標準化が図られます。
送り状印刷:ドットプリンターとの格闘 📝⚔️
Kintoneでの送り状作成が進む中で、最後の課題として残ったのが、ドットプリンターでの印刷における「位置合わせ」問題です。
Kintoneの帳票レイアウトがピクセル単位であるのに対し、ドットプリンターの専用伝票はインチやポイント単位であり、この単位の違いが精密な位置合わせを困難にしています。
印刷物の枠内に正確に印字するためには、「ストックフォームに目盛りを印字し、それを基準にKintone側で位置を計測・調整する」という細やかな対応が求められます。
デジタル化を進める上で、アナログな既存設備との連携は避けて通れない課題であり、その解決に向けた戦略を練っています。
手形受払表の自動化:RPA導入への展望 🤖✨
手ごわかった経理業務の一つである手形受払表(Excel)の改善にも着手しました。
係長が弥生販売の入金明細書データ(入金区分「401」「402」「403」)を活用できる運用ルールを確立してくれたことで、自動化への道筋が見えました。
今後は、提供されるデータをもとにExcelでの「名寄せ」や「金額の合計」といった加工プロセスを自動化する仕組みを構築します。
さらに、同様の集計業務が他にも3種類あることから、将来的にはRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入し、これらの定型業務をワンクリックで完了できる状態を目指します。
これにより、月末の集計作業にかかる労力を大幅に削減し、業務効率を劇的に向上させる見込みです。
営業支援:顧客満足度アンケートの刷新と行動心理学の活用 🤝💖
Google Formで転記作業をゼロに ⏱️📈
営業部門では、ISO監査対応も兼ねた顧客満足度アンケートのデジタル化を推進しています。
従来の紙ベースのアンケートからGoogle Formへの移行を提案し、営業課長からもその利便性に驚きの声が上がりました。
Google Formの最大の利点は、回答がGoogle Spreadsheetにリアルタイムで反映されるため、転記といった手作業が一切不要になることです。
これにより、アンケート実施後の分析作業が迅速に行えるようになり、業務効率が大幅に向上します。
まずはこの利便性を実感してもらうことで、DX推進への意識を高めています。
回答率向上と本音を引き出すアンケート設計 🧠💬
アンケートのデジタル化は手段であり、お客様の本音を引き出し、回答率を高めることが最終的な目的です。そのため、行動心理学の要素を取り入れたアンケート設計のアドバイスを行いました。
主なポイントは以下の通りです。
- 記述式の極力排除: タブレットやスマートフォンでの文字入力の煩わしさを解消するため、記述式の質問を最小限に抑えます。
- Yes/Noの2段階評価: 5段階や3段階評価ではなく、直感的に答えやすいシンプルな2択形式を推奨。質問数も20〜30問程度に絞り、回答者の負担を軽減します。
- 「No」回答時の深掘り: ポジティブな「Yes」の回答はそのままに、ネガティブな「No」の回答があった場合にのみ、さらに深掘りした質問に進むロジックを採用し、改善点を具体的に把握できるようにします。
また、回答率を高めるために、営業担当者がお客様の元へ訪問し、タブレットを使って一緒にアンケートを実施するスタイルを推奨しています。お客様に寄り添った丁寧なアプローチが、質の高いフィードバックを得る上で不可欠であると考えています。
今回の奮闘記を通して、老舗企業のDXがいかに多岐にわたり、一つ一つの課題に真摯に向き合うことで着実に前進しているかをお伝えできたかと思います。アナログとデジタルの融合、そして何よりも「現場の気づき」と「人の力」が、DX成功の鍵を握っています。
これからも、この全国シェア80%を誇る老舗企業が、デジタルの力を最大限に活用し、さらなる進化を遂げる姿を、コンサルタントとして全力でサポートしてまいります。 次回の進捗もお楽しみに!🚀
コーポレートサイトhttps://www.rin-tech.netを開設しました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。


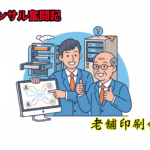

コメント